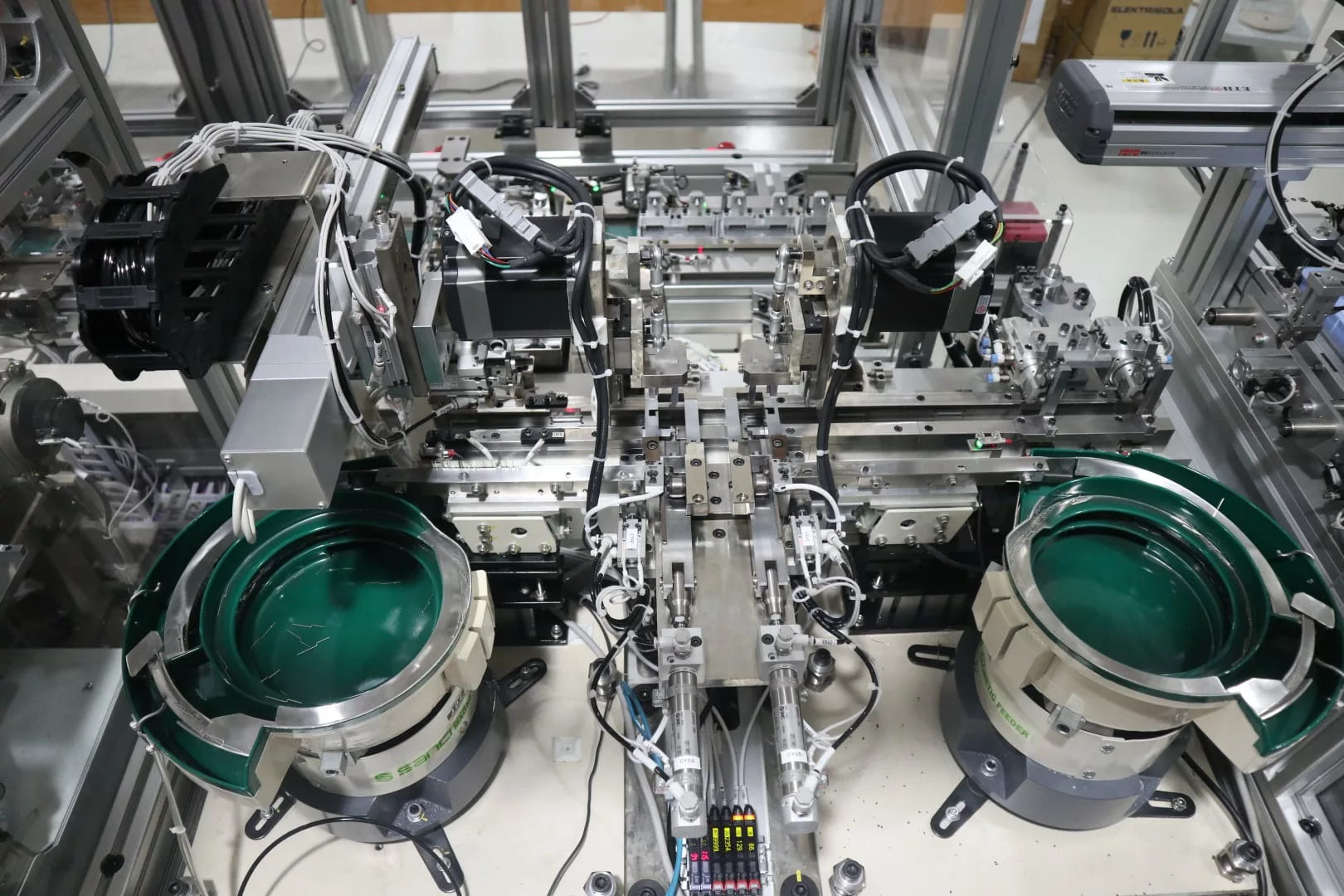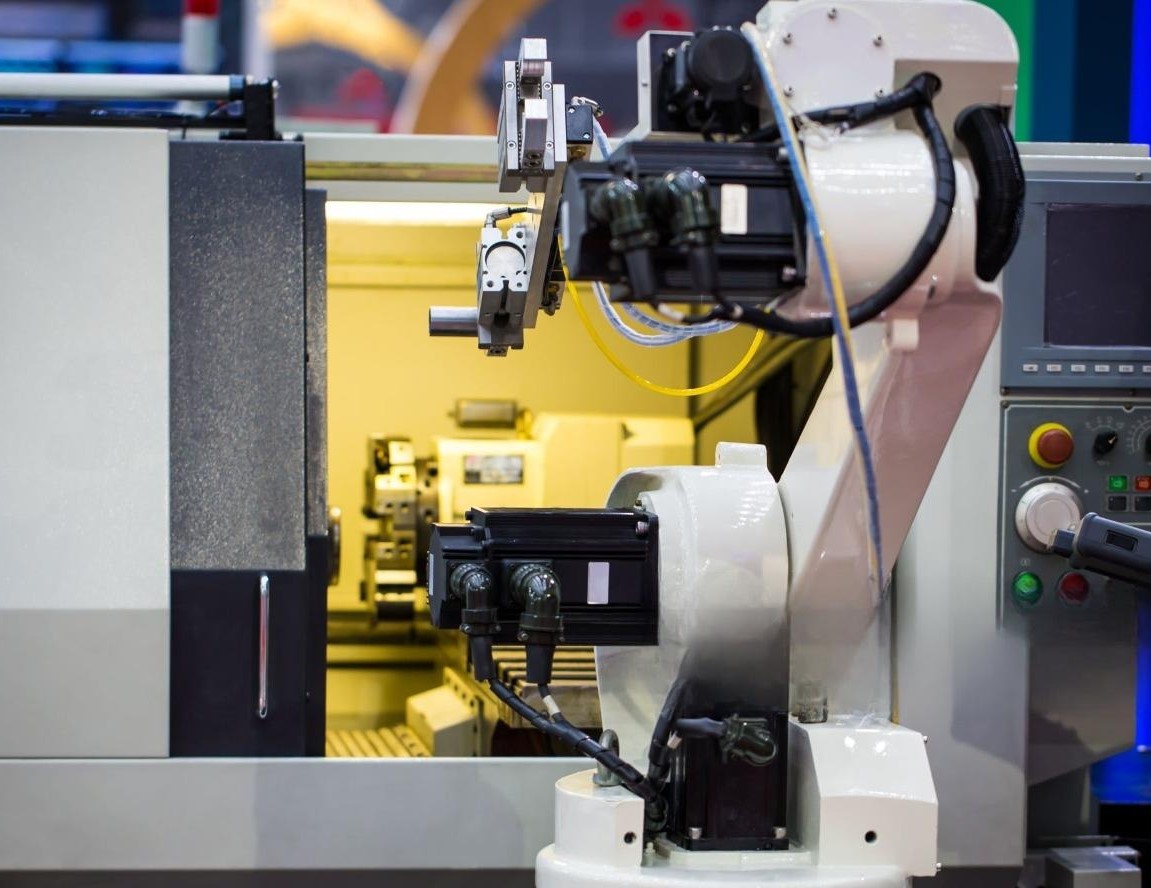機械設計の基本は「図面通りに部品が作られること」です。しかし、設計段階で加工のしやすさ(加工性)を無視すると、製造現場でトラブルが発生したり、納期遅延・コスト増加につながります。
加工しやすい設計とは、加工方法・工具・材料の特性を理解し、無理なく・効率的に・高精度で製作できる設計のことです。これは単に設計者の知識だけでなく、加工現場との連携によって実現されます。

1. 加工しやすい設計の基本原則
1.1. 加工方法に合った形状を選ぶ
部品の形状は加工方法によって得意・不得意があります。
-
旋盤加工:円筒形・軸物に最適
-
フライス加工:平面・角形状に適している
-
穴あけ加工:基本は垂直方向の穴、斜め穴は高難度
-
板金加工:曲げ半径や抜き形状に制約あり
設計者は「この形状はどの加工方法で製作するのか?」を常に意識する必要があります。
1.2. 工具が入りやすい設計にする
工具が届かない形状は加工を難しくします。
-
深すぎる溝や狭い隙間は避ける
-
内部形状にはR(丸み)をつけ、工具寿命を延ばす
-
直角の内角はエンドミルが折れやすい
例:内角にR3〜R5程度の丸みをつけると、加工安定性が向上します。
1.3. 公差は必要最低限に
-
厳しい公差(±0.01mmなど)は加工コストを急増させる
-
実際に必要な精度を見極めることが重要
-
過剰設計は避ける
例:外装カバーに±0.01mmの公差は不要。±0.1mmで十分なケースが多い。
1.4. 材料の加工性を考慮する
材料選定は加工コスト・納期に直結します。
| 材料 | 加工性 | 特徴 |
|---|---|---|
| アルミ | ◎ | 軽く加工しやすい、コストも低い |
| ステンレス | △ | 硬く工具摩耗が早い |
| 鉄 | ○ | 加工しやすいが錆びやすい |
| 樹脂 | ◎ | 切削性良好、ただし熱に弱い |
設計段階で「加工しやすい材料」を選ぶことで、納期短縮・コスト削減が可能。
1.5. 加工順序を意識する
加工工程を複雑にすると段取りや治具が増え、コストが上がります。
-
できるだけ「一方向から加工可能な形状」にする
-
基準面を明確にし、そこから寸法を測れるよう配置する
例:穴の位置を基準面から測れるようにすることで、加工精度が安定します。
2. 加工現場が困る設計例と改善案
| 設計ミス | 問題点 | 改善案 |
|---|---|---|
| 深い溝+直角角 | 工具が折れやすい | Rをつける/溝を浅くする |
| 過剰な公差 | 加工コスト増加 | 必要最小限の公差にする |
| 斜め穴 | 特殊治具が必要 | 垂直穴に変更/加工方法を明記 |
| 硬すぎる材料 | 工具摩耗・時間増 | 加工性の良い材料に変更 |
3. 加工しやすい図面の描き方
設計者は、加工者が迷わず製作できる図面を用意する必要があります。
図面に明記すべき情報:
-
加工基準面(寸法の基準となる位置)
-
公差の範囲(JIS・ISOに準拠)
-
表面粗さ(Ra値など)
-
材料の種類と処理方法(例:A6061-T6、アルマイト処理)
「誰が見ても理解できる図面」が、品質と納期を守るカギです。
4. 設計者と加工者の連携が成功のカギ
-
設計者は現場の制約を理解する
-
加工者は設計意図を理解する
-
双方がレビューを重ねることで「加工しやすい設計」が実現
設計と製造の橋渡しをする姿勢が、品質・コスト・納期すべての改善につながります。
5. まとめ:加工性を考慮した設計で品質とコストを最適化
加工しやすい設計は、設計者と加工者の協力関係によって生まれます。
-
加工方法に適した形状を選ぶ
-
工具や公差の制約を考慮する
-
材料選びや加工順序を工夫する
こうした配慮が「現場が喜ぶ設計」につながり、最終的に製品品質・コスト・納期の最適化を実現します。
加工性を考慮した設計支援は IDEA へ!
「この形状は加工できる?」「もっと加工性を高めたい」
そんなお悩みに、設計と加工の両面から最適な提案を行います。