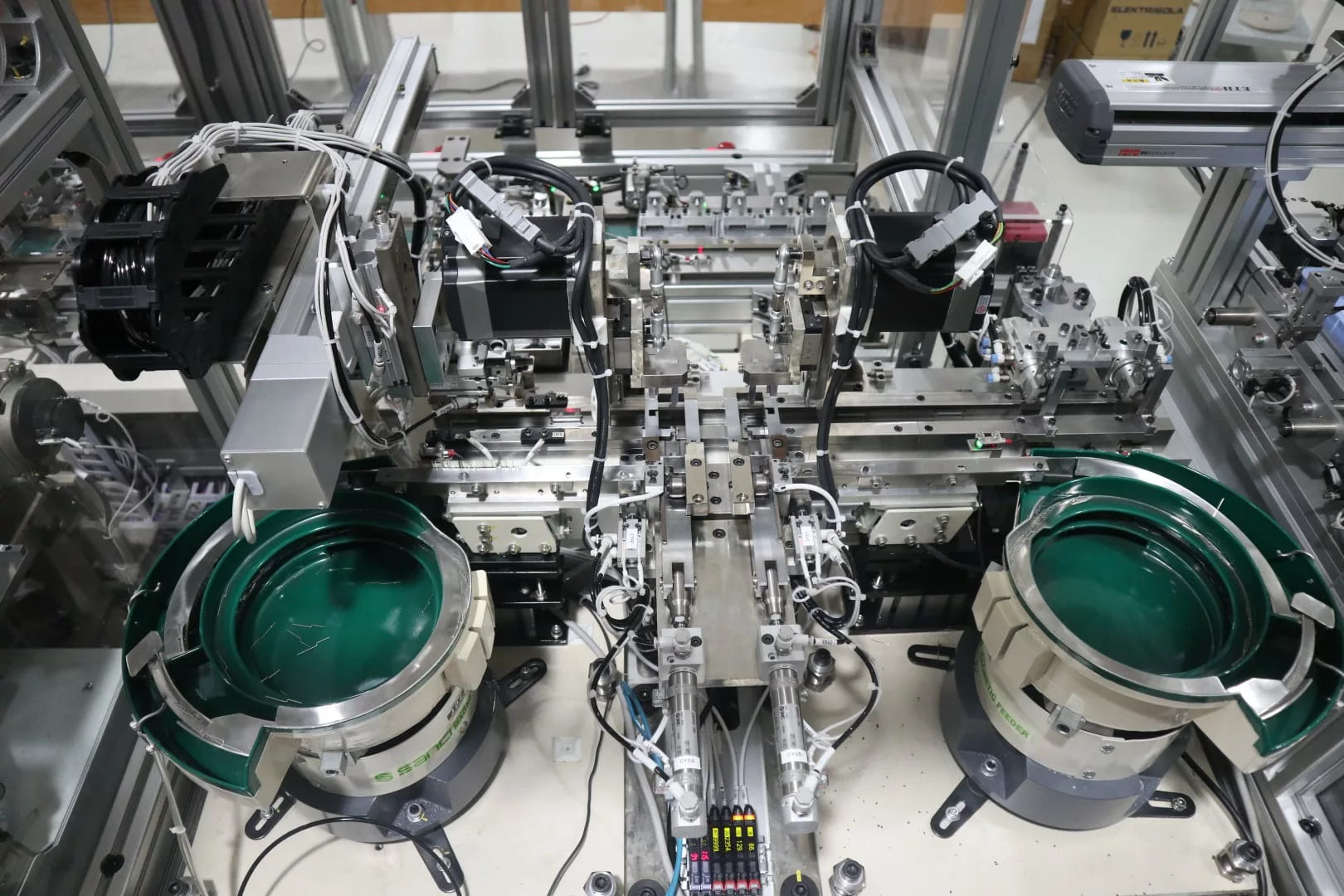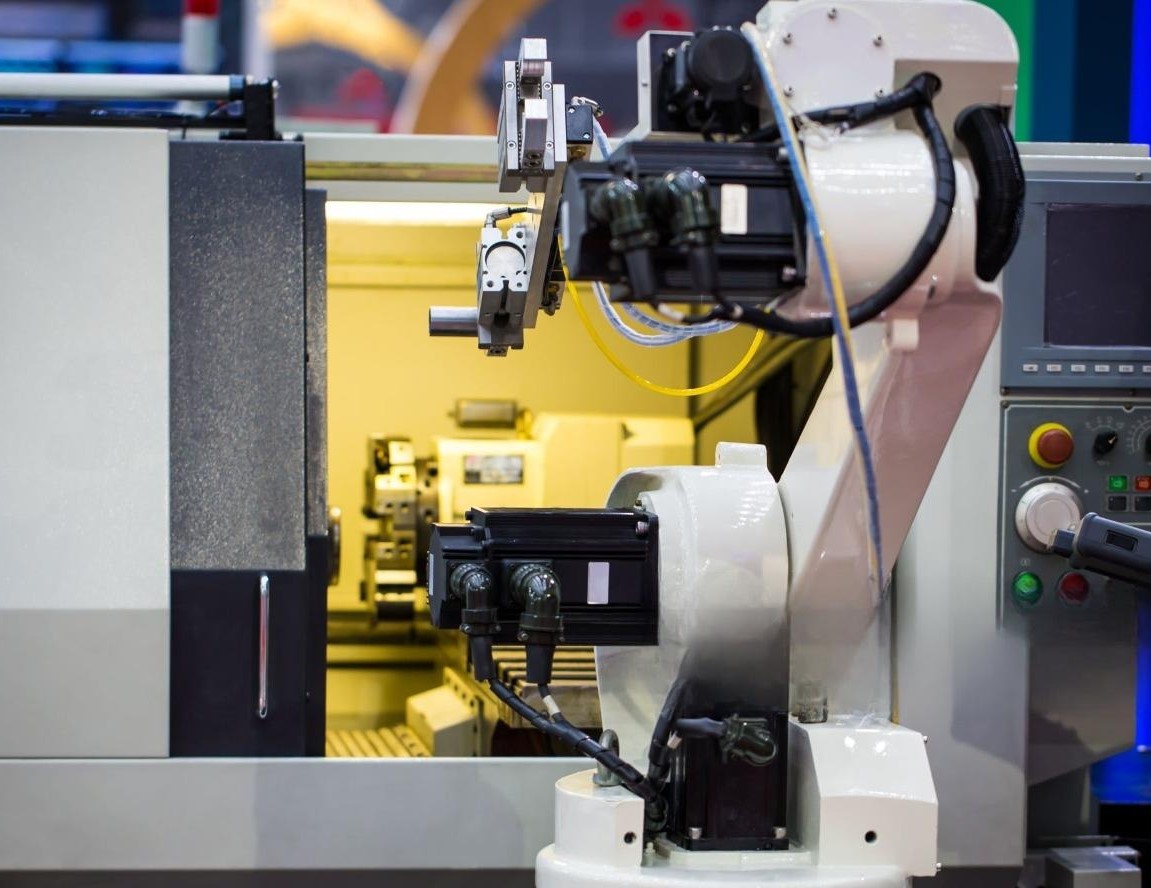機械製図では、設計者の意図を正確に伝えるために、図面上に必要な情報を過不足なく記載することが求められます。しかし、すべての形状や面を詳細に描くと、図面が煩雑になり、かえって読みづらくなることもあります。そこでJIS(日本産業規格)では、投影図の簡略化ルール に基づき、図面の簡略化や不要部分の省略に関するルールが定められており、効率的かつ明確な図面作成が可能になります。
本記事では、JIS規格に基づく不要部分の省略方法、簡略化の原則、投影図の扱い方、そして実務での注意点について詳しく解説します。

1. なぜ省略が必要なのか?
図面の目的は「必要な情報を正確に伝えること」であり、「すべてを描くこと」ではありません。以下のような理由から、省略や簡略化が推奨されます:
- 図面の視認性を高める
- 読み手の理解を助ける
- 作業効率を向上させる
- 印刷や保管のコストを削減する
JIS B 0001では、図面の簡略化に関する原則が定義されており、設計者はこれに従って図面を構成する必要があります。
2. 省略できる代表的な要素
JIS規格では、以下のような要素は省略または簡略化が可能とされています:
対称形状の反対側
対称部品の場合、片側のみを描き、中心線で対称性を示すことで省略可能。
繰り返し形状(穴・溝など)
同じ形状が規則的に並ぶ場合、代表寸法と「○個」などの注記で表現。
見えない内部構造
断面図や補助投影図で明示することで、隠れ線の多用を避ける。
標準部品(ねじ・ワッシャーなど)
JIS規格に準拠した部品は、記号や略図で表現可能。
長尺物の中間部
シャフトやパイプなど、長さが重要でない部分は「切断記号」で省略。
3. 投影図の簡略化と省略ルール
JISでは、三面図(正面図・平面図・側面図)を基本としつつ、必要に応じて投影図の数を減らすことが認められています。
原則
- 必要な形状・寸法・関係性が伝わる範囲で省略可能
- 省略した面は、他の図で補足するか、注記で明示する
- 誤解を招く省略は避ける(例:穴の位置が不明になるなど)
例
- 単純な部品:正面図+寸法のみで十分
- 対称形状:正面図+中心線で片側省略
- 複雑形状:断面図や補助図を追加し、隠れ線を省略
4. 実務での簡略化の判断基準
簡略化は「省略しても問題ないか?」ではなく、「省略することで誤解が生じないか?」を基準に判断します。
判断ポイント
- 加工者が寸法・形状を正しく理解できるか?
- 検査者が基準を明確に把握できるか?
- 組立者が部品の関係性を誤解しないか?
- 図面の読み手が追加説明なしで理解できるか?
5. 省略に関するJISとISOの違い
JISとISOは簡略化の考え方において大きな違いはありませんが、表記方法や記号の使い方に若干の差があります。
| 項目 | JIS | ISO |
|---|---|---|
| 対称形状の省略 | 中心線+注記 | 同様だが記号表現が異なる場合あり |
| 標準部品の略図 | JIS記号に準拠 | ISO 128に準拠した略図あり |
| 省略記号 | JIS Z 8315で定義 | ISO 5456で定義されるが柔軟性あり |
海外との図面交換では、略図や省略記号の意味が異なる場合があるため、凡例や注記で明示することが重要です。
6. よくある省略ミスと対策
- 対称形状の省略で寸法が片側しか記載されていない
- 繰り返し穴の数が注記されておらず、加工者が誤解
- 長尺物の中間省略で全長寸法が不明
- 対策:省略する際は必ず補足寸法・注記・記号を併用する
結論
図面の省略と簡略化は、設計者の判断力が問われる重要な工程です。JIS規格では、視認性と正確性を両立するためのルールが整備されており、これを活用することで図面の品質と効率が大きく向上します。
IDEA Groupでは、JIS規格に準拠した図面作成を通じて、設計業務の標準化と製造現場との連携強化を支援しています。図面の簡略化や省略ルールに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連記事:機械設計の基礎知識|JIS規格に基づく図面の作成基準 – Idea Group